誰にでもケガをするときはあります。
しかし、その中でも防ぐことができるケガもあるのです。
それは主に「肉離れ」「捻挫」「疲労骨折」です。
それぞれのケガをするリスクなどやどうしたらいいかなど解説しています。
最後まで読んでケガのない身体作りをしましょう。

主なケガの種類とリスク
肉離れ
スポーツしてる人が一番気をつけなければならない怪我の一つです。
「所詮肉離れやろ?」
「肉離れごときで」
って思ってる人!!
それは間違いです。
肉離れは本当に時間がかかってしまう怪我で再発も多い怪我の一つなんです。
世界的に見ても多くの選手が悩まされてる怪我です。

肉離れを起こしてしまうリスク
- ウォーミングアップ不足
- 疲労
- 柔軟性不足
- 過去の肉離れの既往歴
- 加齢
- 水分不足
- 左右差
などがリスクになります。
捻挫
よく捻挫をしてしまう有名なところが足首です。
足首の中でも「足関節内反捻挫」というのが多いのが捻挫です。
これはどういう捻挫なのかというと内にひねってしまった捻挫です。
サッカー・ラグビー・アメフトをしている人たちからすると捻挫は日常茶飯事になっています。
そのため、かなり軽視されやすい怪我でもあるのです。
しかし、捻挫から他のケガ(例:肉離れ、半月板損傷など)を起こしてしまうリスクもあるのです。
「ただの捻挫!」という認識ではなく、捻挫でも治療をして、リハビリをして、万全の状態で復帰しましょう。

捻挫のリスク
- 放置することで変形する恐れがある
- 機能障害が残る
- 再発が増える
など捻挫してからのリスクが多いのです。
疲労骨折
疲労骨折は簡単にいうと『使いすぎ』でなるケガです。
ただ、使いすぎでも身体の使い方や変なところへの負担がかかっていることによってなることも多いです。
そういった面でも普段の歩き方、走り方など細かく見て、負担のない動作などを習得する必要もあるのです。

疲労骨折のリスク
- 急激な運動強度の変化
- 同じ部位の負担、負荷
- 栄養不足
- 不適切なフォーム
など少し気をつければ防ぐことが可能なものばかりです。
ケガが選手生命や競技人生に与えること
一つのケガが今後の競技人生を左右することもあります。
例えば、足首のひどい捻挫をして、その後、捻挫癖がついてしまった。
何回も捻挫したことによって、骨に棘ができて、手術で取らなくなってしまった。
その結果、足首が硬くなって、膝への負担が多くなって、半月板を痛めてしまった。
など起こりうるのです。
直結はしないことも多いのですが、回り回ってケガをしてしまうということもあります。
一つのケガが癖になり、何回も同じケガをすることによって、違う部位のケガをしてしまうということもよくあります。
ケガをするのは仕方がないのですが、次ケガしないようにすることであったり、リハビリをきちんとして、再発の防止などもしなければならないのです。

予防のメリット
ケガを予防することは身体にとって、選手生命にとってメリットしかないのです。
パフォーマンス維持
試合に出続けたり、プレーし続けるためにはパフォーマンスを維持することが大事になります。
ケガを予防することはパフォーマンスを維持させることにもつながるのです。
その理由としては、ケガをしない身体ということは身体をいつでも良い状態にしておくことです。
パフォーマンスを維持させるのも身体を良い状態にしておくことと一緒だからです。
長期離脱回避
ケガをしないということは当たり前ですが、長期離脱をしなくてすみます。
長期離脱をするときは基本的にはケガのときです。
コンディション不良やケガをする一歩手前であれば1週間や2週間の離脱で済む時もあります。
ですが、ひどい肉離れや捻挫をしてしまうと、数週間レベルではなく、1〜3ヶ月の期間で離脱をしなければならなくなります。
長期離脱をしないためにも日頃からケガをしない身体作りが大切になのです。
具体的な策
人によって細かくすることは変わってきますがおおまかに言って3つです。
ストレッチ
トレーニング
リカバリー
他にも栄養などいろいろいうことがありますが、今回はこの3つを紹介します。
また〇〇のケガ予防のトレーニングやストレッチは紹介します。
まとめ
スポーツしていると色々なケガをしてしまうリスクがあります。
その中でもリスクを少しでも落とすことができるケガもあるのです。
中でも「肉離れ」「捻挫」「疲労骨折」は予防することができるのです。
予防しててもなるときはなります。
ケガをしてしまった時は次ならないようにリハビリやケアなどをしましょう。

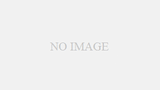
コメント